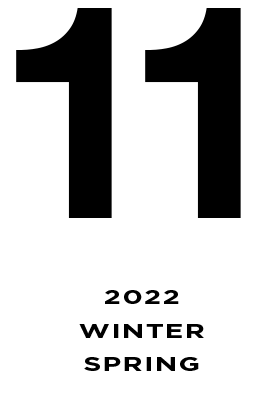青井 茂 株式会社アトム 代表取締役

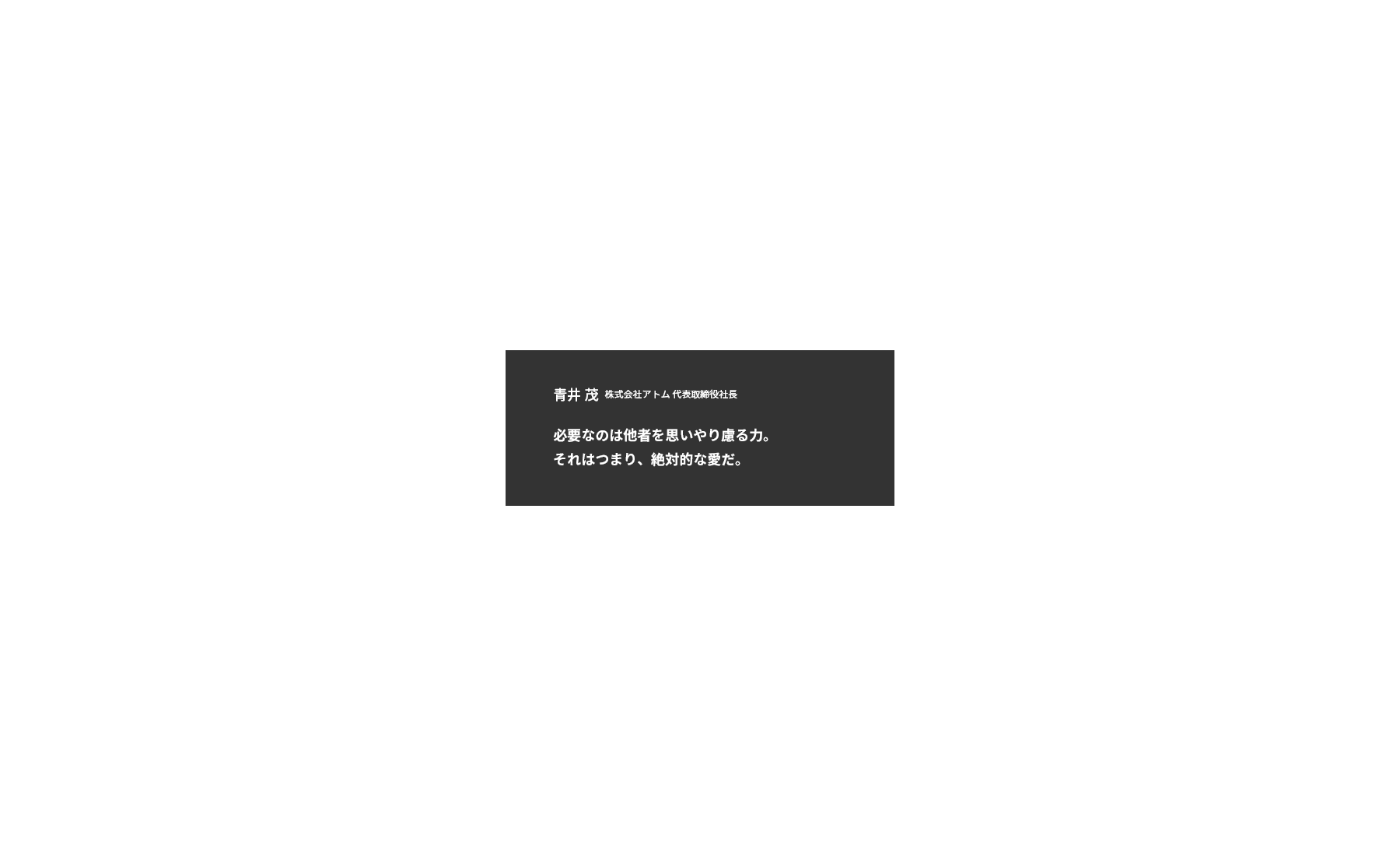
世の中も会社も、あらゆるものは循環する。
それをかなえているのは「神の見えざる手」だと思う。
以前、愛媛の今治に行った時、しまなみアースランドという公園に足を運んだ。公園には地球誕生から46億年の歴史を460メートルの道で表現した「地球の道」があった。「地球の道」の縮尺でいえば、人生100年という時間軸は、わずか0.01ミリだ。そして、株式会社A-TOMが創業したのは1959年だから、その歴史を「地球の道」にあらわせば、たったの0.0063ミリだ。肉眼ですら、見ることができないその時間の短さに、この世はいかに儚く、ちっぽけなものであるか気づかされる。道の最後には、ネイティブアメリカンの諺である「地球は子孫から借りているもの」という石碑が掲げられていた。
悲しいことに、今日も世界中のどこかで戦争が起きている。しかし、どんな状況下でも人は生まれ、明日も明後日も生きていく。そして世界を次の世代へ引き渡し、地球は終わらない循環を繰り返していく。
考えてみれば、この世には循環しないものなどひとつもない。会社だって、循環の連続だ。人が加わり、辞めていく。僕らの会社A-TOMでも、時折、人の入れ替わりは起きるが、僕は、社員が会社を辞めるのは不幸なことだと思っていない。彼らにはA-TOMではなく、他のところにもっと活躍できる舞台があったという、そんな話だ。
会社はジャングルの生態系と同じで、一人一人の社員に特定の役割が求められる。ジャングルにはさまざまな生物が生息し、特異なエコシステムを形成することで、多様な遺伝子が維持され、地球レベルでエネルギーが安定的に循環しているが、人間の活動も同様で、多様性の存在は社会の発展や成長に不可欠だ。多様性があるからこそ、環境は終わりなく続き、社会は多少の浮き沈みはあってもとりあえず持続する。この持続性をかなえているものは、僕は「神の見えざる手」だと思う。世界の秩序はうまい具合にできていて、頭の良い人たちが特段計算しなくとも、「神の見えざる手」のおかげで、すべてがうまい具合に運ばれていく。こうした予定調和の上に社会は成り立っており、世の中のあらゆるものは混沌と静寂を繰り返す。
経済において「神の見えざる手」を論じたのは、ご存知の通り、イギリスの経済学者アダム・スミスだ。ひとりひとりの行動が利己的な動機によるものであっても、それが無数に集積されると、個々人の意図とはまったく関係なく、社会全体の利益となる。そうスミスは説いたが、その言葉はやがて一人歩きし、いつの間にか曲解されてしまった。現在では多くの人が意味を取り違え、「経済は自由な市場競争に委ねればうまくいく」、つまり「自由放任主義」と理解しているが、彼はそんなことは一言も言っていない。彼は経済活動の自由を推奨しているが、そこには重大な前提があり、「国民全体が豊かにならなければ、国は豊かにならない」というモラルが守られているなら、経済活動は自由に行うべきだ、と言っているのだ。つまり、「自分がよければ、他人はどうでもいい」という思考ではダメだということだ。この話は、何も経済に限ったことではない。社会は人間の集合体で成り立っている以上、一人が幸福で充実した人生を歩むためには、おのずと他者の幸福を願う豊かな心が必要だ。
国民全体が豊かになるためには、一体どうしたらいいか。これは、企業経営でも同様に問うべきテーマである。社員全員が豊かに、そして幸福に働くために、会社はどうあるべきか。僕はそのためには、すべての社員が他者を思いやって慮る力、すなわち「慮(おもんばか)り力」を持つ必要があると考えている。
「慮り力」というと顧客サービスの一環のように思われがちだが、実際はあらゆる状況で必要になる。なぜなら、会社はチーム力が勝負だからだ。会社にいれば、誰でも自分の能力や技術、経験に応じて役割が決まってくる。自分にはどんなことができ、周囲からどんな役割が期待されて、どんなポジションに立つべきか。いってみれば、「慮り力」とは「思慮深い想像力」と「機を外さない行動力」の掛け合わせのようなもので、スポーツでも仲間の能力や特性に合わせてパスを出し、攻撃につなげるのは、勝利に不可欠な知性であるように、慮る力の強い企業が高い総合点を誇り、社会に対して価値を高めていくのではないか。
相手のことを想像する。ときには相手に憑依するように、その立場に同調する。そうした「慮り力」の背景にあるのは、仲間や上司・部下や顧客など、他者に対する絶対的な愛だと思う。そうした揺るぎない愛があるからこそ、会社は長く存続し、発展を継続できる。
僕らの会社のA-TOMでも、加わる仲間がいれば、辞めていく仲間もいる。人が辞めていくのは当然寂しさや悲しさを伴うが、それはちょうど樹木が育つとき、間引きすることで幹がぐんぐん成長するようなもので、間引きされた枝葉には他社という台木への接木として、あるいは次世代を担う挿木として新しい可能性が秘められている。そうやって、A-TOMを巣立った仲間が新たな未来を築いていく様子を僕は愛を持って応援したいし、未来はこうして循環していくのだと確信している。
結局のところ、企業を成長させ、働く人を幸せにするために必要なものは愛であり、愛ある行為はひとつの企業から身近なコミュニティへ、そして社会へ、地球へというように、同心円状に拡大し、持続可能な未来を創造する。そこでは安定した経済活動が保持されていて、「自分だけが金を稼ぎ、幸せになれば良い」という短絡的な思考ではなく、常に他者の幸せを願う愛がある。つまり、アダム・スミスは小難しい経済学を説いたのではなく、あらゆる生物が持つべき壮大な愛を描いたのだ。愛ある会社は、働く人にとって優しく、楽しい。しかも、利益が上がるならさらによし。僕はこれからもA-TOMの代表として、愛と「慮り力」を持って勇気ある決断を下し、組織へ手を加えていこうと思う。
日本の雪質は世界一。いま必要なのは、その強みを未来にしっかり活かしていくこと。皆川賢太郎×上村愛子×青井 茂×青井舞彩


― オリンピアンの夫婦が見つめる雪の世界の未来 ―
いま、富山は長い眠りから目覚めようとしている。
既存の価値観を突き破り、人々のくらしを、もっと豊かでワクワクしたものにするために-。
富山変革のストーリーは、すでに第1章を紡ぎ始めた。
青井:日本にいるとあまり感じませんが、世界的には「雪が降らなくなっている」「自然が壊されている」という現状があります。お二人とも、生業としてスキーを続けられていますが、どう感じますか?
上村:現役時代は毎年、秋にスイスで合宿をしていました。スキー場に上がるとき、ゴンドラから雄大な雪原が見えて、その景色がとても好きだったのですが、あるときからクレバス(雪上の大きな割れ目)が目立つようになりました。
皆川:たぶん、20年くらい前から変わってきたと思います。
上村:そのときはまだ地球温暖化が騒がれる前で、私自身、「氷河が消える」というのがどんなことか全然知りませんでした。外国の選手たちと「雪が減っている」という話はしたけれど、「またいつか戻るだろう」くらいにしか思っていませんでした。でも世界的に温暖化が叫ばれるようになり、あとから「私が見ていた景色は、まさに温暖化の象徴だったんだ」と知ったんです。
皆川:地球の表面の3分の2は水で覆われていますが、その大部分が海水で、淡水はわずか2.5%。しかもその淡水の大部分が南極や北極地域などの氷や氷河として存在していて、それらが溶けると海面が上昇して、水没する国や地域も出てきます。実際、子どもの時にスキーで滑っていると、これまで何もなかったところにある年、突然川や滝ができていることも多く、今振り返れば、あの頃から地球温暖化を体験していたんだなと思います。
青井:昨今、さかんにSDGsと言われていますが、お二人はずっと「このままじゃ、地球はまずい」という感覚があったんですか。
皆川:特にこの10年くらいは、温暖化のために雪が降らず、試合が中止になることもありました。でも最近、JOCのミーティングをしていても、夏のオリンピックに関わる人たちは温暖化や環境問題といった感覚が薄いんです。認識の差を感じます。
舞彩:私は一昨年からスキーを始めたのですが、「雪は未来永劫続くもの」という感覚がありました。でも実際はそんなことないんですね。
皆川:2006年には、スイス銀行が標高1500m以下のスキー場に対し、スキー関連事業への融資を停止しています。そもそもスイスは365日雪があり、年中スキーができるところなんです。それなのに、スイス銀行は今後降雪量が減少していくことを前提に、その決定をした。これは大きなショックでした。幸い日本は地形に恵まれ、冬特有の北西季節風が吹くことで日本海側では雪が降ります。でも、日本以外の国や地域では、毎年雪が少なくなっているのが実情なんです。
青井:ということは、温暖化による雪不足から一番遠いところにいるのは日本ということですか?
皆川:日本で雪が降らなくなったら、世界では雪が降らなくなると言われています。
青井:日本は雪資源に対してあまりいいイメージを持っていないけれど、もっと雪資源を誇りに思い、世界にアピールしていかなければならないですね。
皆川:日本の雪質は世界一。でも、日本はそうした資源を持っているのに有効に活用できていません。本当は、とても価値があるものを持っているのに、それに気づいていないんです。
青井:お二人とも世界中で滑っていらっしゃいますが、世界と比較して日本の雪はどうですか?
上村:北海道ではサラサラのパウダースノー、もう少し重い雪を滑りたいと思ったら本州。3歳から滑っていますが、まだ楽しいです(笑)
皆川:僕は、その楽しさはもうないな(笑)。今は雪質というより、山で眺める景観が好き。特にバックカントリーでは、見たことがない景色が目の前に広がっているんです。でも、スキーができないとこの景色を見られない。これがスキーの面白さだと思います。
青井:なるほど、スキーはスポーツであるだけでなく、自然と一体化する手段でもあるんですね。
皆川:この間、青井さんたちと富山のスキー場に行ったんですが、山頂で、いい歳をしたおじさんたちが景色を見ながら「お~」って(笑)。
舞彩:わかります。八甲田に行ったとき、ゴンドラに乗りながら景色を見て、「もっといろいろな景色を見てみたい。そのために、もっとスキーがうまくなりたい」って思いました。
青井:日本は面積の68%が山。それをどう愛でるかということですね。でも、東京のようなコンクリートジャングルにいると、自然の素晴らしさを感じることが難しいと思ってしまいます。
上村:私は年間通して山で過ごすことが多く、SNSで山の景色を発信しています。それはコロナ禍、「山が好きなのに遊びに行けない」という人が多かったから。だから「山は今、こんな感じですよ」と、写真をアップしています。自然を感じたいならぜひ、山へ遊びにきてほしい。そして、心が解き放たれる感覚を楽しんでほしいですね。
青井:二人とも、なぜ指導者にならなかったんですか?
上村:イベントで子ども達に教えることはありますよ。でも私は指導者というより、伝道師になれればいいかな。子ども達にモーグルの楽しさを伝えていきたいですね。
皆川:結局、時間をどう使うかって話だと思うんです。どんなにがんばってもオリンピックでメダルを取れるのは世界で3人だけ。そのための努力は選手時代、必死にやりました。じゃあ今は何をやるかって考えたら、選手時代からずっと考えていたリゾート再生。日本はバブル期にスキー場をたくさん作り、冬季産業を拡大させていったけれど、その分、1か所あたりの価値が下がり、どんどんデフレが進んでしまった。ヨーロッパはスキー場の数を限定して価値を上げ、インフレを図っているのに、日本は真逆だったんです。いま、日本には900か所のスキー場があるけれど、僕はこれを整理して、日本の冬季産業を復興させたいんです。
青井:壮大な夢ですよね。リゾートを再生するって、普通のビジネスパーソンじゃ決して言えない。
皆川:コロナ前、日本政府は「2030年に訪日外国人(インバウンド)6000万人」という目標を掲げました。これを実現するには、東京オリンピックのような「おもてなし」だけでは無理。もっと戦略的に海外から人を呼ぶために、雪は最高の観光資源だと思うんです。この価値をどう発信し、世界へ伝えていくか。そこに、日本の冬季産業再生の鍵があると思います。
愛する街でがんばる若いパワーが、明日の富山をもっと元気にする。

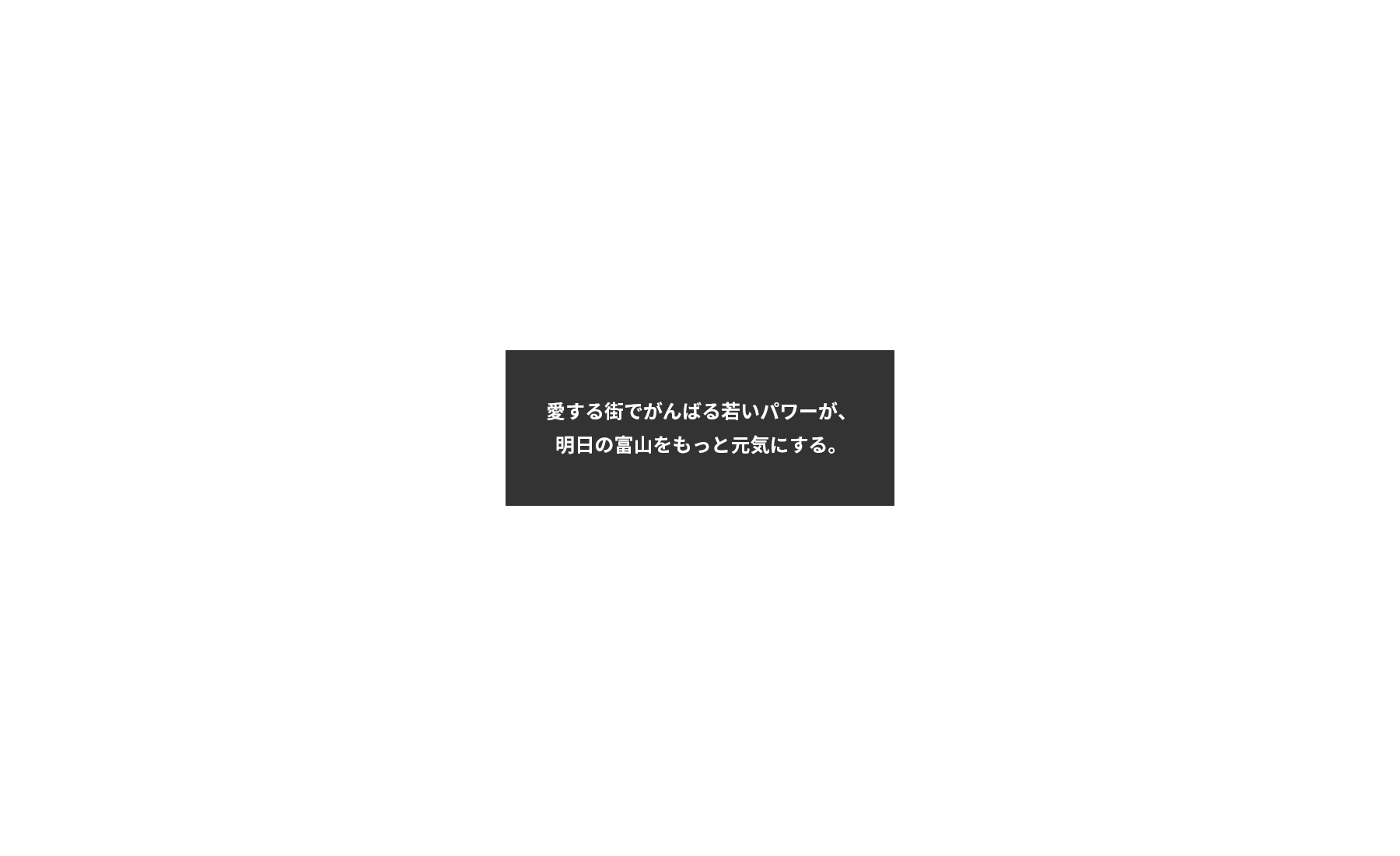
津田:私が美富味で働くようになったのは、以前、接客業をしていたときにお誘いを受けたから。もともと日本酒が好きだったし、再開発が進んでいる注目のエリアで地元富山に関わる仕事ができると知り、即決でした。
長田:私は知り合いの紹介で、美富味で働くようになりました。今、大学4年生で、神奈川の大学に通っています。コロナ前は神奈川に住んでいましたが、早い段階から授業がすべてリモートになったので思い切って家を引き払って富山へ戻りました。現在は週1回、夜行バスで神奈川へ行ってゼミに出席し、あとは富山で過ごしています。
寺岡:僕も富山出身だけど、大学は関東で過ごしました。一度、富山を離れると見えてくることってあるよね。
長田:そうなんです。関東の大学に行って、より一層、地域のつながりは大事だなって気づき、そこからまちづくりにハマりました。来春就職でまた関東へ行きますが、いずれはITとまちづくりを結びつける仕事をしたいと思っています。
柿崎:私は今、大学に通いながら、TOYAMATOでインターンをさせてもらっています。きっかけは、大学で中谷さんの講座を受けたこと。まちづくりをがんばる会社が富山にもあるんだって知り、私もやってみたいって思いました。
中谷:アウトレットの企画を提案に行ったり、イベントを企画したり。いろいろ経験したよね。
柿崎:以前から、もっと多くの人に富山を知ってほしいっていう気持ちがありました。友達のなかにも県外の大学を選び、そのまま戻らない人がいます。その人たちは「富山は何もない」って言うけれど、「何もない」っていうことはまだ富山を知らないっていうこと。もっと富山を知ってもらうために何ができるかなっていつも考えています。
安藤:私はBiBiBi&JURULiのオープニングスタッフとして働いています。「生まれて初めてのバイトだし、新しくオープンするところで、みんなで一緒に作っていきたい」という気持ちで応募しました。
中谷:BiBiBi&JURULiは、富山の食材や食器などを使うのがコンセプト。だからお客さんからいろいろ尋ねられることもあるんじゃない?
安藤:あります。最初は産地などを尋ねられても上手に答えられなくて、とても悔しい思いをしました。私は富山大学に推薦入試で入学したのですが、そのときの志望理由は「自分が生まれた富山をもっとたくさんの人に知ってほしい。そして、一度きりの人生だから、自分を育ててくれた富山に恩返ししたい」ということでした。柿崎さんと同じように、私の友達でも富山から県外へ出て行く人が多く、「富山には何もない」って言います。それがとても残念で、ゼミで知り合った男の子と一緒に富山のいいところを発信する企画もやっています。
堀:私も安藤さんと同じく、BiBiBi&JURULiのオープニングのときからバイトをしていますが、そのあと、美富味がオープンしたときにもスタッフとしてお手伝いをさせてもらいました。今はふたつのお店を兼務しています。
中谷:最初はお客さんに日本酒のことを聞かれても何も答えられなかったのに、みんな一生懸命蔵元や日本酒のことを勉強して、今ではお客さんにきちんと説明できるようになっているのは、本当にすごいと思う。
津田:私は日本酒が好きだったけれど、あまり詳しくなかったんです。でもみんなで日程を合わせて蔵見学に出かけるなど、少しずつ知識を身につけてきました。
長田:実際に蔵元を見学すると、どこでどんなふうに日本酒が作られているか、お客さんにお話できるし、蔵の人の思いもお客さんに伝えられるので、接客でもとても役立っています。
寺岡:僕は美富味やBiBiBi&JURULiよりも早くオープンした、あまよっと横丁の管理を担当しています。あまよっと横丁は、今年で開業4周年。新型コロナの影響で大変なこともあったけれど、何もなかった空間に若者達の賑わいを創出できたことにやりがいを感じます。まちづくりって、とても可能性がたくさんあるんですよ。概念もとらわれないし、考え方もクリエイティブ。関わる人たちのアイデアが徐々に形になっていくプロセスこそ、この仕事のおもしろさだなって思います。
中谷:富山の人たちは、最初の一歩を踏み出すまで時間がかかるけれど、「みんなでやりましょう!」って集まった時の熱量はすごいよね。コミュ二ティも狭いから、人と人のつながりも強いし、距離も近い。僕はこれまで「採算第一」という世界で生きてきたから、TOYAMATOで働き始めたときは、正直とても戸惑いました。でも、お金だけじゃ「人」はついてこない。働くには、お金も大事だけど人も大事なんだなってつくづく思います。
寺岡:ここで働く人たちは、みんな富山が大好き。だからこそ、まずは富山の人たちにもっと富山を知ってほしいって思っているんじゃないかな。
堀:私は日本酒が好きなので、ぜひ、友達に富山のお酒の魅力を知って欲しくて、美富味のお酒をプレゼントしたり、日本酒を一緒に飲む機会を作ったりしています。いま、大学3年生で、来年の就職に向けていろいろな企業でインターンをしたり、大学で学祭の実行委員長をしたりしながら、「私が得意なことや好きなことってなんだろう」と模索しています。そのなかでひとつ見えてきたのが「みんなをひきこむ仕事をしたい」という気持ち。富山には自然や食やお酒などたくさんの魅力があるので、そういうものをもっと多くの人に知ってもらい、みんなで楽しめることができたらいいなって思います。
柿崎:私は美富味で働くまでお酒が苦手だったのですが、ここで働くようになり、いろいろおすすめされてテイスティングを重ねるうちに、だんだん日本酒が好きになってきました。
中谷:日本酒は米と水だけでできていて、富山にはどちらもある。そうしたエリアは日本でもそうそう多くなく、富山の人たちはもっと自慢に思っていいはずなのに、年々、富山の日本酒消費量は減少しています。もっと盛り上げていきたいよね。
寺岡:そのために、あまよっと横丁や美富味、企画によってはBiBiBi&JURULiも連携して、みんなで新しいことを仕掛けていきたいですよね。相互送客もできるし、協働でイベントもできそう。
中谷:特に20代の若い人たちには僕らにはない発想力やアイデアがある。若い人たちと、これまで富山の歴史を築いてきた人たちや、県外の人たちが連携すれば、もっと新しいことも生まれそう。今日集まってくれた人たちは大学生が多いから、いずれはアルバイトも卒業になるんだろうけれど、次に入ってくる若い人たちにも、まちに対する思いは伝えていきたい。そうやって、富山のまちづくりをする人が広がっていけばいいよね。
不動産ビジネスとアート。相反する両者が「ソノ アイダ」で見つけ出した共通言語。藤元 明×嶋 勇人×久保田聡子

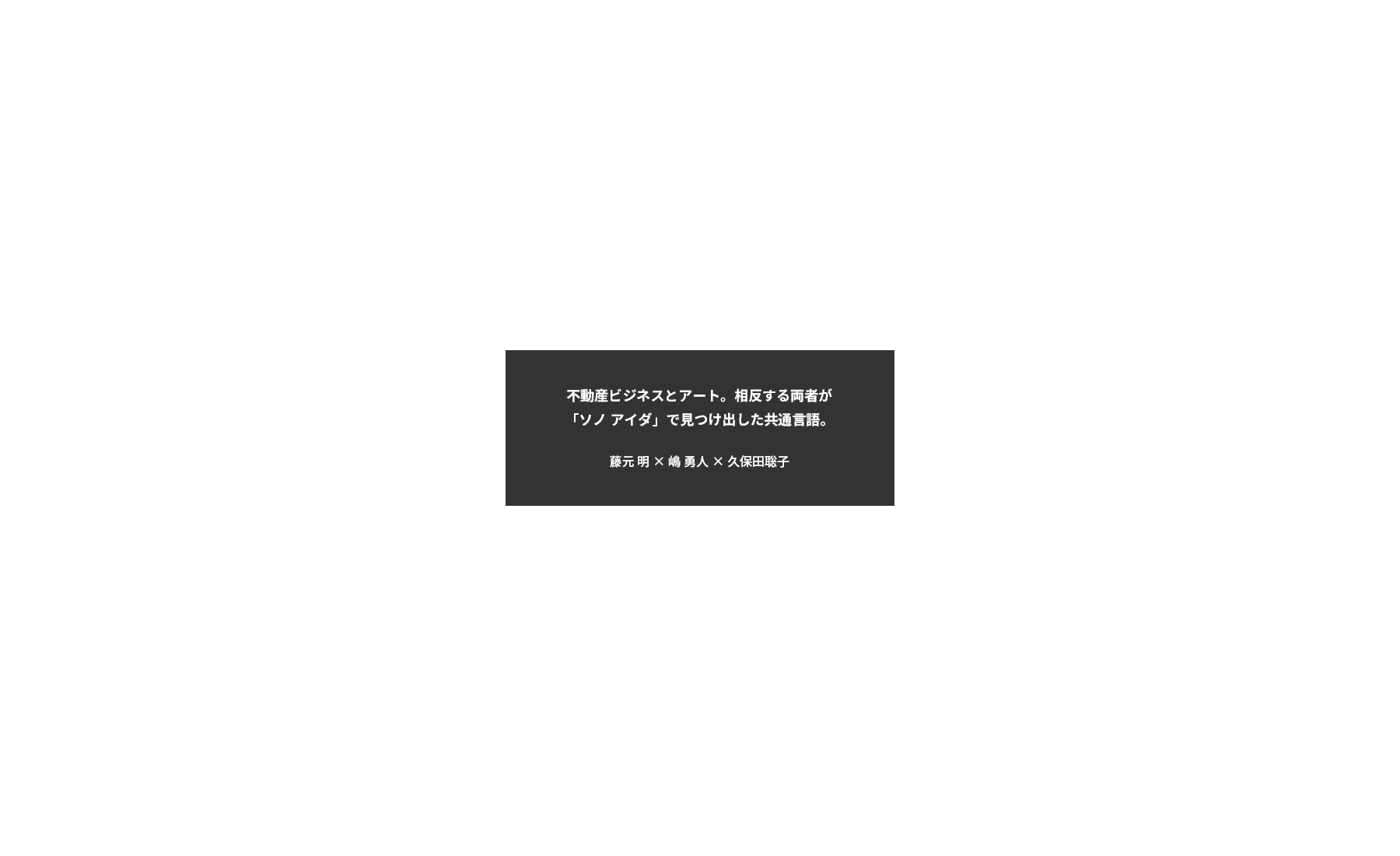
アーティストとビジネスサイドは理解しあえない
嶋:振り返ってみれば最初から苦労の連続だった。「ソノ アイダ」の話を茂さんから聞いたときは「マジか」と思った。面と向かって、「A-TOMにはこういうプロジェクトの知識も経験もない。そもそもビジネスとして成り立つんですか!」って言ったくらい。
久保田:茂さんはなんておっしゃったんですか。
嶋:「なにもないけれど、やる」(笑)
久保田:確かに「先に利益を出すことを追求するのではなく、どういう空間を作ったら街がおもしろくなるのか考えなければ。ファーストペンギンにならないとおもしろくないだろ」っておっしゃっていましたね。
嶋:これをどうやってビジネスにつなげられるかというアイデアはなかったし、それははっきり言って、今もない。でも茂さんは、「アートピースや作家、コレクター、キュレーター、評論家などアートを取り巻く経済圏が集まり、そこに商流が生まれればビジネスになる。マイアミやソーホーだって、アートを軸に地域の不動産価値を上げた。そういうことを、僕は日本でもやりたい」と言ったんだ。「茂さんがそう言うなら……」って、このプロジェクトが立ち上がったんだよね。
久保田:話が決まって賃貸借契約まで2か月ほど。すぐに第1期が始まりました。
嶋:たくさんのアーティストたちと関わるようになり、最初に困ったのが彼らとの共通言語がないということ。ビジネスにおいて投資をするということは、当然、リターンを求めるということだけど、アーティストはそういう発想で生きていない。もちろん彼らにとっても作品を売ってお金を稼ぐことは大切だけど、彼らはお金のために作品を作っていない。アーティストから「金のことばかり、うるせぇ!」と怒鳴られたこともある(笑)
久保田:そうなんですか(笑)
嶋:そのとき僕は「アーティストとビジネスサイドは、理解しあえない」ということを知ったんだ。そして、見ている世界が違うことを受け入れて、落とし所を見つけることが大事だって思うようにしたんだ。これは僕にとって大きな転機だった。
久保田:私もこのプロジェクトを通して、考えがどんどん変わっていくのを感じます。私はずっとバレエを続けてきたのですが、ダンサーの熱が会場全体に広がる高揚感や、地道にリハーサルを続ける苦労を知っていて、その両方がここにはある。通りすがりの人がたくさんこちらへ視線を送ってくるなか、実際に部屋へ入って来る人は少ないけれど、なかには毎週訪れる学生さんもいます。確実に彼の人生は変わったと思うし、そういう仕事に携わっていることをとてもありがたいと思いますね。
嶋:正直言えば、今でも常に矛盾はあるよ。利益を追求しようとすれば、作品が売れることが一番だけど、売れる作品を作ることは彼らの美学ではない。だけどプロジェクトが始まって半年以上経ち、確実に僕自身も変化したのを感じている。なにより、アートにまったく接点のなかったこの僕がアーティストの作品を買ったんだから。そのアーティストの作品を見て、直感で「かっこいい、欲しい」って思った。こんなふうに自分が変わったという変化がうれしかったな。
久保田:この半年間、私たちはアートに接する濃度が高かったから。
嶋:今は、どこかで見たテナントばかりが並ぶ街じゃなく、この情緒的な価値を世の中が認めてくれれば、作品が売れる売れないじゃないレベルで大きな変化になる可能性があると思うんだ。実際、某大手デベロッパーから建設中のビルにテナントとして入りませんか、って声をかけられたし……。
久保田:今、私が考えるのは、アーティストがA-TOMと組む価値。A-TOMは不動産会社だけど、こんな一等地にビルを持っていないし、人的リソースもない。
嶋:よく言えばアートの理解者。悪くいえば、お金でのサポーター。それだけでなくA-TOMにしかできないことを考えて、A-TOMならではの価値ある街づくりにつなげていきたいね。
人が集まる理由は人
もともと「ソノ アイダ」は2015年に始まったプロジェクト。空き物件や貸し物件などの「都市の隙間」を利用して、アート展示やイベントなどを行ってきました。この新有楽町ビルで始めたのは2021年12月で、1年半かけて行う予定です。
これまではひとりで主催してきましたが、さすがに1年半の長丁場になると誰かサポートが必要ということで、以前からの友人であるA-TOMの青井さんに相談したら「我々が主催するので、ぜひ一緒にやりましょう」と言ってくれたんです。うれしかったですね。日本では、作品を購入して支援してくれることはあっても、アーティストとしての活動自体をサポートしてくれることはほぼありません。「もっとフレキシブルな形で、アーティストが企業と一緒にアート活動を構築する」という新しい選択肢にしたいと考えていました。
とはいえ、実際にプロジェクトがスタートし、難しいと思ったのは、決定権者にたどり着くまでに時間がかったり、場所に制約が多くあったりすること。アーティストは普段個人で活動していて、こういう組織体に入って動くことはほとんどありません。現場では協力的な雰囲気であっても、美術館・ギャラリーのような展示するための環境ではないので、双方アイデアを出しながら歩み寄り一つずつ着地させていく。難しい進行ですが、でもこれが企業とアートの協働なのだと、僕たちアーティストにとってはとても良い経験になっていると思います。
「ソノ アイダ」のおもしろいところは、都市、それも都心の路面店にアーティストのアクティビティを持ち込んでいるところです。アーティストが作品を作るにはスペースが必要ですが、都心ではそのスペースを見つけることができず、制作環境は郊外へ離れがち。作品だけが都心に集まり、アーティストは都市にいないというドーナツ化現象が起きています。でも本当におもしろいのは、アーティストのアクティビティ。やっぱり、人が集まる理由は人なんです。アーティストの活動や状況を丸ごと見せればパフォーマンスとして成立する。それはアーティスト一人の力ではとてもできないので、A-TOMや三菱地所など企業とお互い出来ることを持ち寄って、従来の資本主義的な価値観だけじゃなく、まったく新しい価値観をみんなで一緒に作っている。それをこの有楽町という、皇居のすぐそばでできているということもおもしろいし、こういう活動がどんどん広がれば、東京という均質化してしまった街の、新しい魅力につながるんじゃないかな。多くの企業は「儲かるか、儲からないか」という視点で物事を見ています。しかも、一つの企画、今期などの短いスパンが基準。でもこういうアートプロジェクトは、「儲かる、儲からない」という既存の価値基準をこえた、新しい価値観を獲得できる可能性がある。実際世界の都市では、アートの力で新しい価値観を作るという試みは日常的で、成功事例も多い。たとえばマイアミは世界規模のアートフェア「アートバーゼル」を誘致して、危険な街から アートの町へと変貌させましたし、ニューヨークのミートパッキングもそう。今では世界中からアートと人が集まります。でも日本では、「アートの力で町おこし」とか、観光コンテンツとして捉えられていて「いい作品を作ってくれれば街が活性化する」とか、アート任せにしてしまう。アートに任せるのではなく、アートを利用すして拡張すべきなんです。特に、アートを利用したまちづくりは、A-TOMが不動産会社だからできること。現場のリアリティとアーティストのロマンチシズムを融合しながら協業で街を盛り上げるのが本当の姿。そのためには、アーティストも好きな絵を描くだけだったり、企業にサポートをねだったりするだけでなく、企業の期待に答えられるよう目的を共有し達成するという振る舞いが欲しいところ。企業にはもっと時間軸を長くもって、長期的に価値を生み出すことに挑戦してほしいですね。
アートを育てる文化の再生と不動産ビジネスの進化を両立させる
嶋:東京の駅前に、ものすごく古いビルがあるんですよ。そこを建て替えたら誰でも儲かる。普通、ビルの価値は「坪単価×面積」で決まるじゃないですか。でも僕は、そこにアートという切り口で付加価値をつけていけたらって思うんです。藤元さんはどうですか。
藤元:まず、この議論がアーティスト側じゃなくて企業側から出るのがおもしろい。一緒にプロジェクトを始めて半年以上、少しずつ変わってきたのを実感してます。もし、不動産に容積だけじゃない価値があるのなら、アートもその選択肢の一つとして考えてもらえるとありがたい。それに応えられるアーティストが不足しているのは重々承知しているけれど......。
嶋:アーティストが不足しているのはなぜですか?
藤元:そういう経験のある人材が少ないから。欧米にはアーティストを育成する文化があるけれど、日本では極端に規模が小さい。でも20~30年くらい前はもう少しありましたね、それがバブル崩壊や価値観の個人化とともに消えてしまった。
嶋:A-TOMとしては、そういう場所をアーティストに提供できる一助になりたい。この20年で失われた場を取り戻すことを愚直にやっていくというのも、我々の挑戦であり、ミッションじゃないかと思います。あとは、それをどう持続的にしていくか。誰かがひとりでふんばるんじゃなく、どうやってみんなで分散していくか。仲間づくりも含めて、これから考えないといけないなと思います。