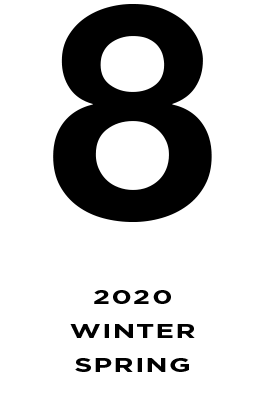青井 茂 株式会社アトム 代表取締役

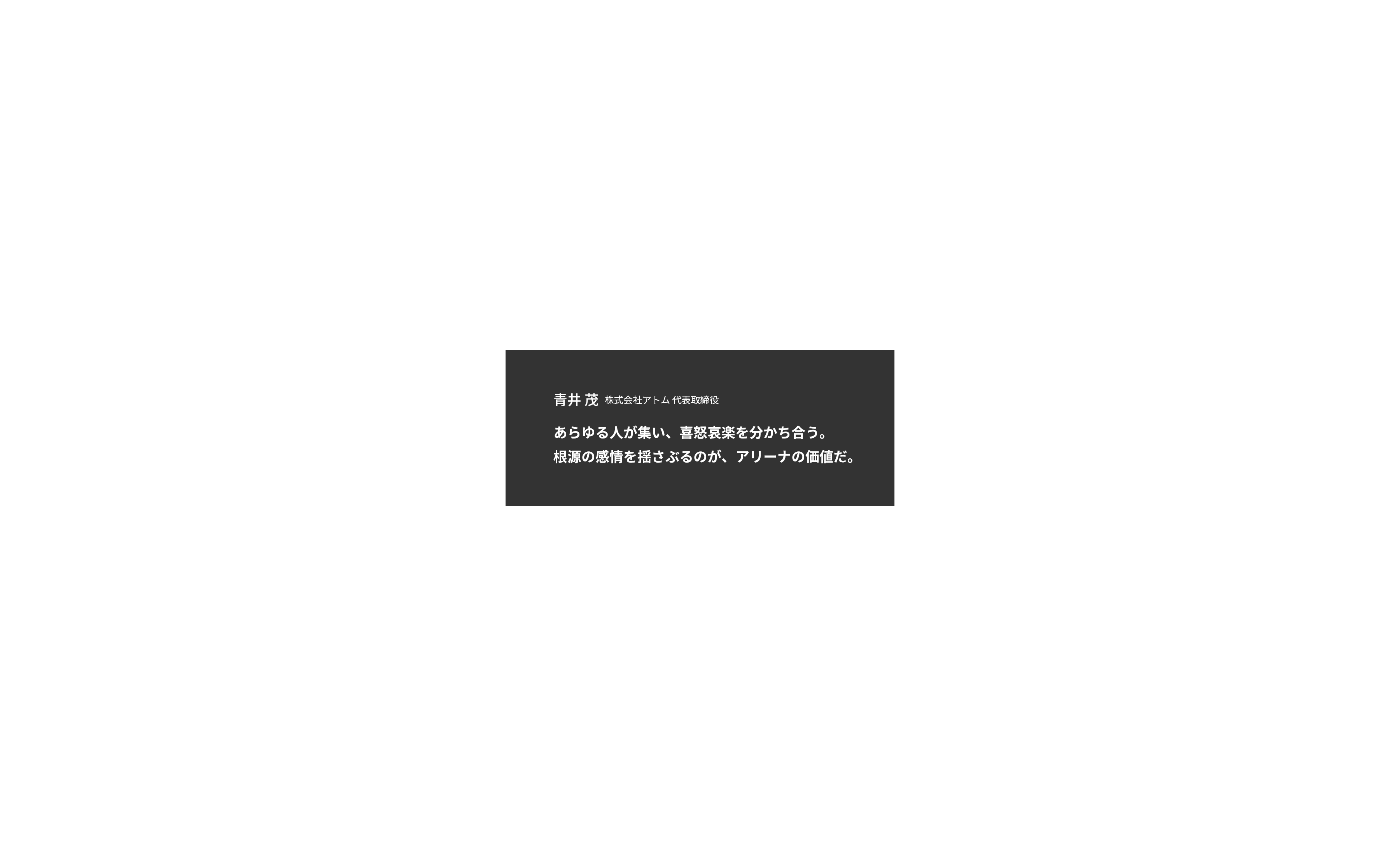
これを書いている今、日本ではラグビーW杯が開催されている。残念ながら、日本チームは大熱狂のなかで戦いを終えたが、その死闘は今でも僕らの胸に深く刻まれている。僕は、4大会連続で現地のスタジアムに出向き、W杯を観戦しているが、今回ほど、応援に熱が入った大会はなかった。横浜国際総合競技場で行われたスコットランド戦では、約7万人の観客が勝利を祈った。競技場は異様ともいえる興奮の渦に包まれ、僕はその観客席のど真ん中で、ますます「アリーナを作りたい」という気持ちを強くした。祖父の故郷であり、僕自身のルーツでもある富山に、世界に誇れるアリーナを作るのが僕の夢だ。
僕はこれまでたくさんの国を訪れ、アリーナやスタジアムを視察してきた。どの街でも、アリーナやスタジアムはその街のプライドであり、文化の象徴だった。街の人々はアリーナやスタジアムを誇りに思い、地元のチームを情熱的に応援した。欧米諸国に比べて、日本はスポーツの歴史が浅いが、いま、日本のスポーツビジネスも変わりつつある。かつては重厚長大産業がプロスポーツチームのオーナーを勤めていたが、今はITやゲームなどさまざまな産業も参入し始めた。指導技術は進化し、アスリートの技量は一昔前に比べて格段に成長している。そして観戦者である僕らも、自由視点映像など最新技術の恩恵を受けて、以前よりもっと大迫力で試合を観戦できるようになった。今後、ウェアラブル端末の進化が進めば、僕らは特殊なアイグラスを装着するだけで、まるでフィールドの中に立っているかのように、空間の音や匂い、湿度までも感じられるようになるかもしれない。ただ試合を「見る」だけではなく、「感じる」とか「想像する」とか、別の楽しみ方も登場するかもしれない。
だが僕は、どれだけIT技術が進化しても、リアルな感動をダイレクトに求める人間の本能的欲求は抑えられないと思っている。いま、パソコンやスマホに代表される電子機器の発達は、人々から恐ろしいくらいに身体性を奪い去ったといわれているが、果たして本当にそうだろうか。むしろ、ITが進化すればするほど、人間は身体性について高い関心を持つようになったのではないか。テクノロジーが進化するほど、人間の欲求はシンプルになり、「もっと五感に刺激を受けて、感動したい」という欲求が強くなっているのではないだろうか。
それが顕著なのが、音楽産業だ。ライブやフェスなどのエンタテインメント事業は、2000年以降業績を伸ばし続けている。CDの売上が激減する一方、ストリーミング産業が急成長を見せ、音楽が当たり前のように日常に溢れるなかで、人々はなぜ、お金を払って会場へ出かけ、大混雑のなかで音楽を聞こうとするのか。それは、「生の感動を大勢と共有したい」という、人間本来の欲求からくるのではないか。事実、ライブやフェスなどの人気にはSNSの普及が大きく貢献していて、それにより、ただの音楽イベントが音楽を介したコミュニケーションの場に変化した。
それはスポーツでも同様で、たとえば超巨大なスタジアムの観客席をたった一人で独占し、超一流のプレイヤーたちの超絶な技巧を間近に見たとしても、僕はそれほど感動しないと思う。すごいなあと感嘆の声を漏らすことはあっても、先日のスコットランド戦のように、拳を振り上げて絶叫し、声を枯らしながら応援することは決してない。あの場には、同じ感情を共有する仲間がいた。名前も顔も知らず、その場限りの仲間だとしても、僕らは確かに一つの感情を共有し、深いところで繋がっていた。そうした感情の共有こそ、試合やライブを生で見ることの意義であり、僕らが本能的に求めるものだ。
本来、スポーツは戦争のメタファーであり、国民がその戦況と結果に熱中するという同様の構造を持っている。特にオリンピックやW杯のような国際大会においては、「スポーツは戦争の代替行為である」という過激な意見さえ聞こえてくる。それは言い過ぎだとしても、人間は元来、攻撃的な一面を持っていて、選手たちに自分自身の姿を投影しているのは事実だと思う。自分と同じ、生身の肉体である彼らが目の前で超人的な白熱プレイを披露する。その影にある過酷な練習や厳しい自律を想像しながら、そんな選手たちの闘いぶりを間近に見るたび、僕はいつも、「自分はこのままでいいのか」というある種、自戒のような気持ちを感じる。「自分はいま、本気なのか」「闘いから逃げていないか」「甘えていないと言えるか」。そんな自省が胸に突き刺さるのを感じながら、僕は拳を振り上げ、選手たちを全力で応援するのだ。そこにはテクノロジーが入り込む余地などなく、僕はあらゆる五感を総動員して、彼らの一挙手一投足を感じ取る。そして数万人もの思いが互いにぶつかり合い、増幅しながら、スタジアム全体を巻き込んでいく。その瞬間、僕の心は激しく揺さぶられるのだ。その揺さぶりこそ、人間が本能的に求めているものであり、人生においてそうした揺さぶりが多ければ多いほど、僕らの人生は実り多く、豊かになっていくのだと思う。ちょうど、畑が何度も掘り起こされたり、耕されたりして、土壌を豊かにしていくように。
僕が描く「富山アリーナ」は、あらゆる人が集い、感情を共有する場所だ。どれだけ最先端テクノロジーを備え、設備が立派でも、「感情を通して繋がりたい」という根源的な欲求が満たされなければ、アリーナの価値はない。そこではたくさんの人が喜怒哀楽を表現し、共に喜び、涙を流す。数万人もの人が挑戦者の熱量に触れ、瞬時の感情を分かち合い、同じ経験を共にする。そんな分かち合いの豊かさこそ、いま、日本が最も必要としているものであり、僕は富山アリーナから、そうした豊かな文化を発信したいと考えている。
米田惠美 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事 公認会計士


挑戦の始まりは「共通言語」を作ること
溝口:米田さんとの出会いは中学時代のバスケ部。その後、2019年3月、あるビジネス誌に掲載された米田さんの取材記事を読み、世の中にインパクトを与える活動をされていると知って、ぜひお話をお聞きしたかったんです。
米田:ありがとうございます。久しぶりにお会いでき、うれしいです。
溝口:記事を読むと、2018年3月にJリーグの常勤理事に就任したあと、苦労も多かったようですね。
米田:大変だったのは組織に「共通言語がなかった」ということです。具体的にいうと、目指すべきところは何で、それはどんなストーリーで向かっていくのか。互いの仕事はどんな影響があるのか、とても見えづらかった。「何の効果を得ようとしているのか」「どんなリターンが得られるのか」などのビジネスでいう管理会計的視点も根付いていませんでした。あとは、P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Act)のうち、Pが圧倒的に少なくて。組織は完全にDo文化で、とにかくアクション重視でした。それはそれでいい面もありますけどね。
溝口:利益を目的にした組織じゃないから?
米田:それもあると思います。大企業がPを重要視して、Dにたどり着かないと揶揄されるのと真逆でした。
溝口:どうやって対処したんですか?
米田:まずは「ビジョンと中期経営計画を立てよう」と号令をかけました。もちろんはじめからきちんと作るのは難しいので、週1回幹部を集めたセッションを半年間ファシリテーションして。自部署のプレゼンをしてもらったり、宿題を提出してもらったり、お題を出して互いに意見交換したり、いろいろなアプローチを考えました。
溝口:どれくらいで変化を感じられました?
米田:1年くらい経った頃です。結局、ボトムアップではなかなかビジョン・中計が仕上がらなくて、25周年の期日がきたので、最後は私のほうで手を動かしました。そのドラフトを提示したら、「俺たちの考えはこれじゃない」という声があがったんです。“自分ごと”になっていないと、そんな声はあがりませんよね。「じゃあ、これをたたき台として、作ってね」と言い、そのドラフトをベースにして、何度もみんなで話し合ってもらいました。そうした対話を通して、自分たちのストーリーに変えていってもらったんです。
溝口:組織文化を変えることに対して、抵抗や反発はありませんでしたか?
米田:もちろんありました(笑)。今までビジネスとしてのフレームワークがなくても、組織として成り立っていたのだから、ビジョンや中計なんて必要なの?と散々言われました。組織によっては時代の変化に対して臨機応変に対応できるよう、あえて作らないところもあるけれど、Jリーグの場合は目の前のアクションに追われ、組織が疲弊していると思った。個々が感じているミッションもバラバラで、組織が分裂しそうになっていた。だからまずはそこから作ろうと思ったんです。作っている過程では必要性をあまり感じないのだけど、あとで振り返ればそういう“地図”があってよかったと思うはず。組織の雰囲気が変わり、一人一人が自分の役割を認識し始めたのは、最近ですかね。
人の発言を通して自分に気づく
溝口:いまA-TOMはミッション「2030」を掲げ、2030年までに売上20億の会社を30個つくることを目指しています。そのために、一人一人の社員に事業を“自分ごと”として考えてもらい、主体的に関わって欲しいと思っているんですが、当事者意識を持ってもらうために、組織はどう動けばいいと思いますか。
米田:私が行ったことのひとつが“かわら版”。幹部を集めたセッションでは、誰がどんな発言をしたか、それに対して私がどう感じたか、全部赤裸々にまとめて社員や各クラブの人たちに配っていました。たとえば、「~してくれない」「『上』が~」のような言葉が出てくれば、私は「こういう発言が出るということは、当事者意識がないということですよね」とコメントします。それを読めば、誰でも「こういう発言はまずい」と気づきますし、発言した本人も自覚するでしょう。かわら版は、内省のためのツールにしていました。
溝口:それはすごい! 反発も強そうです。
米田:確かに反発もあったと思います。でも、当時は反発すら出てこなかったんです。表向きはイエス集団、でもなかなか指示どおりには回らないし、飲んでいる時には未来の話というより、愚痴をこぼすことが多かった。反発の声がちゃんと表面化されるようになったのも、大きく前進した証と思います。
Jリーグに対する情熱の根源
溝口:米田さんはこれまでJリーグとは関係ない分野で活躍されてきたんですよね。それなのに、Jリーグに対する情熱はどこから湧いてくるんですか。
米田:私がJリーグに参画したのは、村井満チェアマンに声をかけてもらったから。村井やクラブの人の話を聞いたり、Jリーグについて散々調べたりするうちに、Jリーグには日本人の価値観を大きく変えるくらいのポテンシャルがあると感じたんです。何より、この組織がやってきたことや理念、現場で働いている人たち一人一人の思いが尊い、美しいと思った。スポーツの多面的な価値と、Jリーグという組織が持つポテンシャルに触れて、これは他の組織では代替できないなと思ったんです。
溝口:でも、組織にいる人たち自身は、その価値やポテンシャルに気づいていない、と。
米田:サッカー好きな人だけじゃなく、もっと多くの人にJリーグは価値を届けられるよ!と言いたかった。いま振り返れば私はずっと「日本の課題を根本的に解決するには何が必要なんだろう」というパーツを探していたんだと思います。そしてJリーグと出会い、スポーツというコンテンツは間違いなくそのツールになると思った。
溝口:米田さんが「変えたい」と思う現在の日本とは?
米田:無関心だったり、世の中の状況を嘆き、「政府が悪い」とか「自治体の対応が悪い」とか、誰かのせいにしちゃうマインド。本当は自分から動けば変えられることもあるのに、誰かがやってくれるでしょうと受け身な姿勢。それが寂しいし、社会保障費の増大などいろいろな社会課題に繋がっていると思っていました。だからこそ、誰かの笑顔のために1歩踏み出す人を増やしたい、「ヒトゴトからワガコトへ」が私の中でのキーワードでした。
溝口:なるほど。「Jリーグを変える」より、もうひとつ上の階層に「日本をなんとかしたい」という自分なりのミッションがある。だからそれだけの情熱を持つことができるんですね。働く上で、女性としての難しさを感じることもあったのでは?
米田:もちろんありました。でも、「私はこういう人間だ」「こういう働き方が心地いい」ということを自分自身で認識し、それをきちんと周囲に発信できれば、性別問わず、個としてお互いに認め合えるはず。一人一人の思考がそんな風に変わっていけば、組織自体が許容性を持ち、一人一人の役割や居場所がちゃんと作られると思うんです。
溝口:米田さんが今後、挑戦してみたいことはなんですか。
米田:社会を変えるツールは食かスポーツだろうと思っているんです。今はJリーグを舞台にして、自らの経験や知見を生かすことが、私の役割だと思っています。でももしかしたら数年後には、まったく別のアプローチで社会をよくするための活動をしているかもしれない。そして数十年経った頃には「村民食堂」を開きたい。子どももお年寄りも、みんなが一緒にご飯を食べて触れ合えるような食堂を開いて、“食堂のおばちゃん”をやるのが夢ですね!
Restaurant MAISON Sota Atsumi

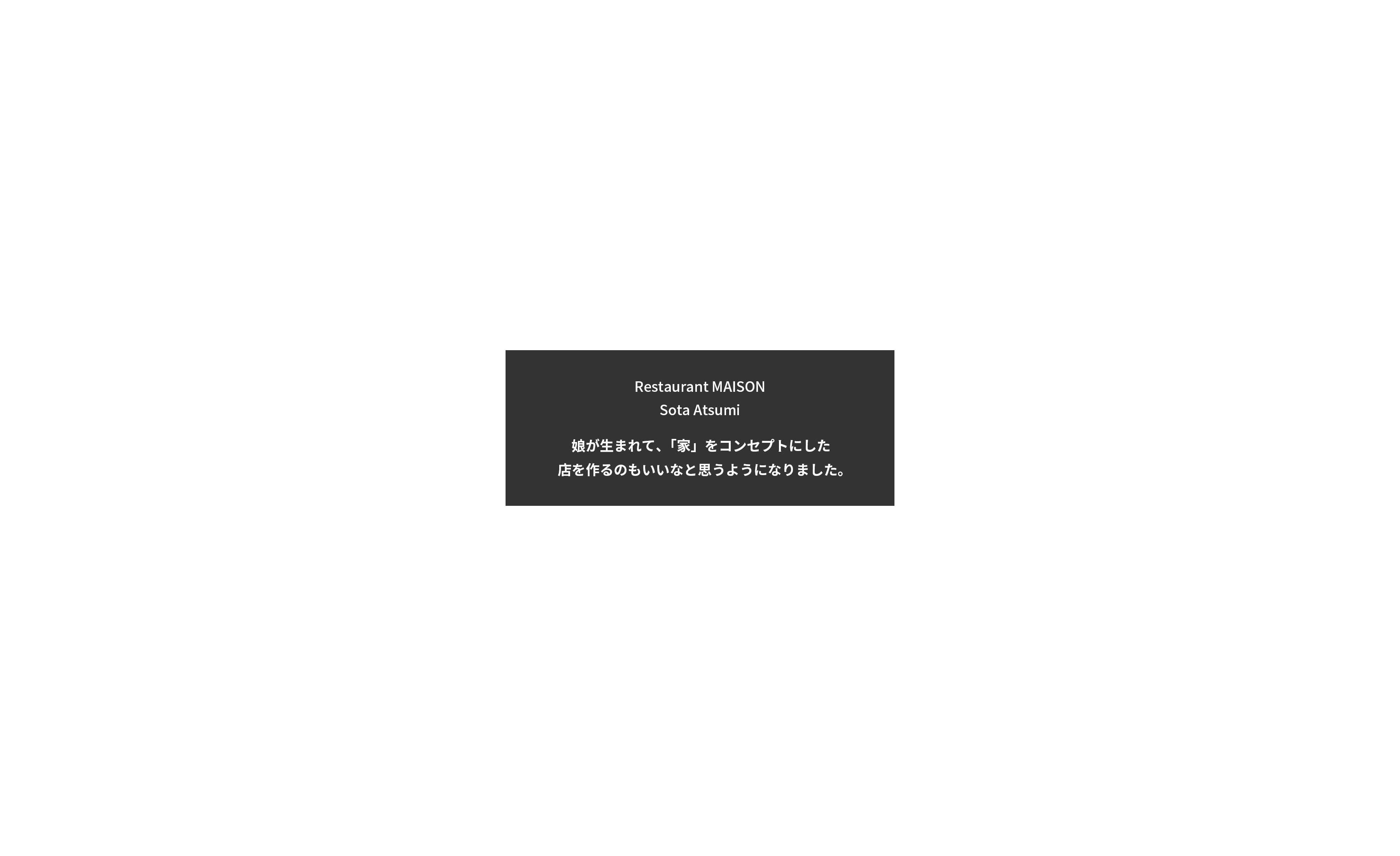
「家」へゲストを迎えるように
ビルやアパルトマンが並ぶ一角に、突然、三角屋根の一軒家が現れる。どこか懐かしく、郷愁を感じさせるような佇まいは、まさに「家(MAISON)」と呼ぶのにふさわしく、そこがレストランであることを感じさせない。ここは2019年秋、パリにオープンしたフランス料理店「レストラン メゾン」。いま、最も注目されている若手シェフ、渥美創太氏がパリの11区に開店した。
渥美氏は19歳で渡仏し、「トロワグロ」や「ステラマリス」などで研鑽。26歳の時に「ヴィヴァン・ターブル」のシェフに抜擢され、2014年からは、100年以上続く「クラウンバー」のリニューアルに伴い、オープニングシェフを勤めた。その後、満を辞して2019年に「レストラン メゾン」をオープン。
「それまで自分の店を持ちたいという気持ちはあまり強くなかったのですが、生産者さんとの付き合いが深くなるにつれ、『自分で選んだ食材を自由に使いたい』など、次第にやりたいことが増えてきたんです」と渥美氏は語る。
「レストラン メゾン」を作る上で大事にしたことは、ガストロノミーだけどアットホームで、自分の家にゲストを招き入れるような感覚だ。店は2階がダイニングで1階がサロンという構造になっており、ゲストは大きなソファがゆったり置かれたサロンで出迎えられたあと、階上のダイニングで食事を楽しみ、食後はまたサロンへと、まるで家へ招かれたかのように寛ぐことができる。壁と床には、フランス全土から集められた赤茶のテラコッタが22,000枚も使われており、雰囲気に温もりを加えている。
学生時代はプロのスノーボーダーをめざしていたが、大怪我が原因で断念。その後、食通の祖父に影響を受けて幼い頃から料理に興味を持っていたこともあり、辻調理師専門学校へ進学した。そして、卒業と同時に渡仏。フランス料理を学ぶなら絶対に現地で、という強い意思があったからだ。
「今でこそパリには日本人シェフが増え、活躍している人も多くなったので、国籍の違いで苦労することも少なくなりました。でも僕がパリへ来た頃にはまだ大変なことも多かったんです。決して仲が悪いわけではないけれど、フランス人のシェフたちは『日本人には絶対、仕事を取られたくない』と必死になっていて、ちょっとした嫌がらせみたいなものを受けることもありました」
フランス料理は、フランス人の郷土の誇り。それを日本人に、しかも、当時はまだフランス語も流暢に話せなかった渥美氏に任せてたまるか。フランス人シェフたちにはそんなプライドもあったのだろう。だが、それでも渥美氏は負けなかった。日本人ならではの繊細な感覚や勤勉さ、なにより持ち前の根性と精神力で、どんな経験も糧にした。
人との出会いに恵まれている
「僕は昔からラッキーなことに、人生の要所に立つたび、仲間が現れるんです」
渥美氏はそう語る。アートの仕事をしていて、公私にわたって人生の良きパートナーである奥様しかり、共に料理の道を追求してきた同僚しかり、そして、この「レストラン メゾン」を一緒に創り上げた建築家田根剛氏しかり。人生の節々において、渥美氏は「いい人との出会いに恵まれている」と言う。
「僕は決してコミュニケーションが得意なわけでなく、むしろ口下手なタイプなのに、どうしてだかわからないんですが……」
そう話す渥美氏だが、彼の人柄に少しでも触れれば、彼が人を惹きつける理由がよくわかる。彼は決してお世辞を言ったり、媚を売ったりしない。相手が金持ちだろうと、社会的地位の高い人だろうと、有名人だろうと、常に自然体で接していて、話す言葉に嘘がない。そんなナチュラルな人柄が多くの人を惹きつけるのだ。
「有名人だからっておべっかを使うわけじゃない。だから、周りから持ち上げられたい人にとっては僕が生意気に見えるみたいで、マイナスになることもあるんですけどね」
そう言って渥美氏は笑うが、裏返せばそういうタイプの人間は、渥美氏の人生においては交わる必要のない人だ。世のなか、人の顔色をうかがわずに生きることは、いい顔を作ることよりも難しい。だが、渥美氏はなんの気兼ねもなく、ナチュラル(自然体)に生きている。その姿はまさに、畑に育つ野菜が太陽におもねいたり、雨雲に媚びたりすることなく、ただまっすぐ成長していく姿のようだ。
一切、迷いも衒いもない料理
ナチュラル(自然体)という言葉は、渥美氏の人柄だけでなく、料理にもよく表現されている。「一皿の料理を作る裏では、たくさんの人が関わっています。僕ひとりで料理ができるわけでなくて、誰かが魚を釣らなければならないし、誰かが牛を育てなければならない。魚や肉や野菜を、丹精こめて作ってくれた生産者の人たちが、『こいつなら自分が育てたものを大事に扱って、素材の持ち味をありのままに引き出してくれるだろう』と信頼し、僕に食材を任せてくれる。そんな料理人でありたいと思っています」
素材の一部を強調して料理に仕立てるのではなく、素材を丸ごと使って存分に魅力を引き出す。そんなダイナミックで直感的な料理は、渥美氏の持ち味だ。通常、多くの美食家が集うガストロノミーの場合、いろいろな食材を無理やり集め、無駄を出してしまうことも多いが、渥美氏がめざすのはその対極だ。目の前に並んだ食材から受けたインスピレーションをヒントに、食材の香りや旨味、甘みなどを掛け合わせ、無駄なくおいしさを生み出していく。嘘やごまかしが一切なく、どこまでも自然体。そんなスタイルに共感して、実際、レストランへ食事に訪れる生産者も多いという。
そうした料理の姿勢が身についたのは、「ヴィヴァン・ターブル」でシェフを務めたときだ。ナチュラルワインに精通したオーナーのもと、生産者とのつながりを大事にすることや、食材を無駄にしないことを学んだ。ここにも渥美氏にとって、人生の転機といえる大事な出会いがあったのだ。
「僕はこれまで夢や将来を考えることがほとんどありませんでした。いつも目の前のことに全力を注いできたから、先のことを考える余裕などあまりなかったんです。でも2年半前に娘が生まれて初めて、『家』をコンセプトにした自分の店を作るのもいいな、と思うようになりました」
この先、どんなことが起こるかわからないけれど、今は、「レストラン メゾン」を大切に育てていくだけ。将来、なにかご縁やつながりがあって、日本かまた別の場所に舞台を移すことになるかもしれないけれど、今はただ、目の前のことに集中したい、と渥美氏は言う。ただひとつ、今、持っている夢は「娘とカウンターで寿司を食べること」と言って微笑んだ。
「レストラン メゾン」のスタッフは日本人のほか、フランス人、コロンビア人、韓国人と多国籍だ。ダイニングの中央に置かれた8mのテーブルは20人でシェアできる長さであり、日夜、ここでは国籍も年齢も属性も違う人たちが、身近な距離で同じ料理を楽しんでいる。しかし、「レストラン メゾン」はただ食事をするための場所ではない。世界中のあらゆる「家」が家族を見守り、一人一人を育む存在であるように、「レストラン メゾン」もまた、皆が同じ料理を口にしながら互いの夢を語りあい、新しい何かを生み出す場所なのだ。ここでは、同じ空間を共有する人たちの間で、常に新しい縁が紡がれていく。そして、渥美氏が手がける、迷いも衒いもない、ただ自然体の料理だけが、人と人との縁の真ん中にある。